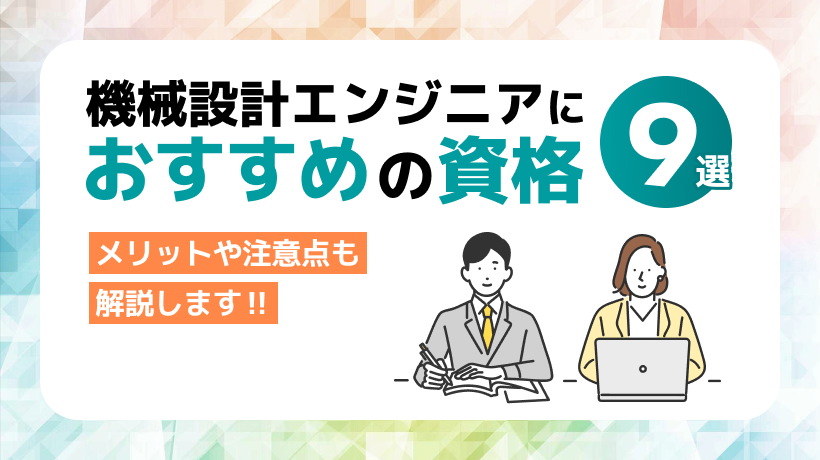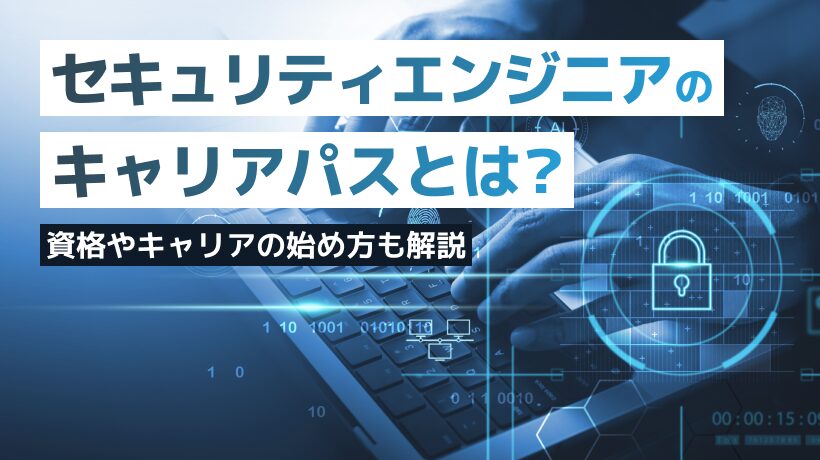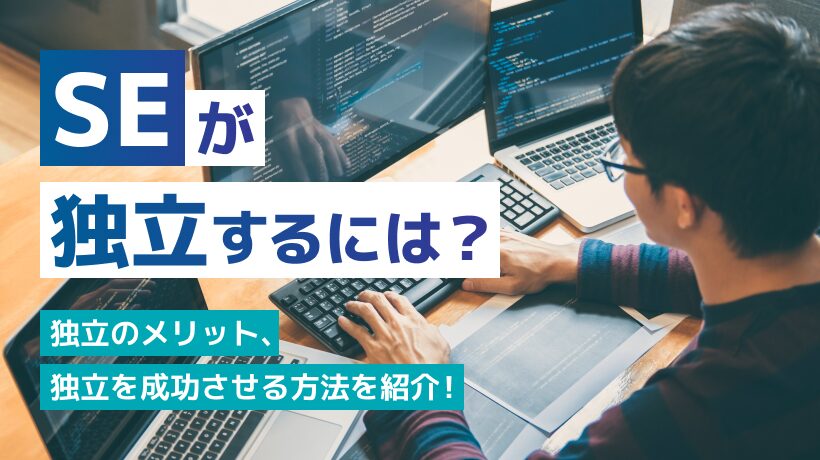機械設計エンジニアとして働くうえで、資格の取得はスキルアップやキャリア形成に大きな影響を与えます。資格を取得することで、専門知識の証明や収入アップの可能性が高まり、転職やキャリアアップにも有利に働くでしょう。
機械設計エンジニアに就職・転職を検討している人や、機械設計エンジニアとしてのキャリアを考えている人の中には、「どのような資格を取得するべきか」と悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、機械設計エンジニアが資格を取得するメリットとおすすめの資格を紹介します。さらに、資格を取得するときの注意点についても解説しているのでぜひ参考にしてください。
『機械設計エンジニアの仕事を徹底解説!年収、必要な知識、やりがいも紹介』
機械設計エンジニアが資格を取得するメリット
機械設計エンジニアが資格を取得することでどのようなメリットが得られるのでしょうか。
収入アップの可能性がある
機械設計エンジニアが資格を取得することのメリットの1つとして、収入アップの可能性が高まることが挙げられます。
企業によっては特定の資格の取得に対して合格報奨金や資格手当を支給している企業があります。こういった企業であれば給与が上がる可能性があります。こういう手当は一度のみ報酬が与えられる場合と毎月の給与が上がる場合があります。
また、資格を取得することで、機械設計に関する専門的な知識の習得やスキルの向上を証明できるため、より専門的な業務に関われるようになったり、企業内でのポジションが上がったりすることで昇給できる可能性もあります。
このように、資格を取得することによって企業からの評価が得られ、収入を高められる可能性があるのです。
信頼性が高まる
機械設計エンジニアは資格を取得することで、クライアントやパートナーから自身に対する信頼性を高めることができます。
資格は一定の知識やスキルを保有していることを証明するものなので、プロジェクトにおいて専門家としての説得力が増しますし、評価されやすくなるでしょう。それによってプロジェクトを円滑に進められるようになる可能性がありますし、案件の獲得などにも有利に働くはずです。さらに、資材や製造業者、外注設計会社などのパートナーとのやり取りにおいても、資格があることで説得力が出ますし、技術的な要求事項の調整などもしやすくなるはずです。
特に、国家資格や認知度の高い民間資格を取得すれば、クライアントやパートナーに対して専門性をより明確に示せ、信頼を得ることができるでしょう。
このように、資格を取得することで、企業からエンジニアとしての専門性やスキルを認められ、信頼を得やすくなります。
キャリアの選択肢が広がる
機械設計エンジニアは資格を取得することでキャリアの選択肢を広げられる可能性があります。資格を取得することでより上の役職や管理職などに就ける可能性が高まりますし、転職や独立などの新しいキャリアにつながるかもしれません。
資格を取得すれば履歴書や職務経歴書などに書くことができ、能力だけでなく適性や熱意などもアピールすることができます。それによって転職時や独立したあとの営業時に有利になるはずです。企業によっては内定後や入社後に特定の資格の取得が必須となる企業もあります。
このように、機械設計エンジニアが資格を取得することは、昇進・転職・独立といった多様なキャリアの選択肢を広げることにつながる可能性があります。
機械設計エンジニアにおすすめの資格9選
機械設計エンジニアは資格を取得することでさまざまなメリットが得られるとわかりましたが、どのような資格を取得すればいいのでしょうか。ここでは機械設計エンジニアにおすすめの資格を9つ紹介します。
1.機械設計技術者試験
機械設計技術者試験は、機械設計エンジニアの総合的な能力を認定する民間資格で、安全で効率的な機械を経済的に設計するための知識や技術を評価します。
機械工学の基礎から、設計業務に必要な計算、構想図の作成などのスキルを問われ、技術者のスキルレベルに応じて3級・2級・1級の3段階に分かれています。3級は機械工学の基礎的な知識が問われ、2級・1級に進むにつれて、より高度な知識と技術が求められます。特に1級は実務経験を活かした問題も含まれ、難易度が高いとされています。
2.技能士(機械・プラント製図技能士)
技能士(機械・プラント製図技能士)は、技能検定の中でも機械・プラント製図に特化した技術を持っていることを証明できる国家資格です。機械設計では正確な図面をもとに部品の製造や組み立てを行うので、製図のスキルが必要になります。
主に機械製図の手書き作業やCAD作業、プラント配管製図作業が試験内容に含まれています。この資格を取得することで、設計意図を正確に伝え、図面の作成・修正を効率的に行う力が身につき、機械設計における精度向上や業務効率化につながり、実務において大きな強みとなるでしょう。
3.CAD利用技術者検定
CAD利用技術者検定は、一般社団法人コンピュータ教育振興協会が運営する民間の資格試験で、取得することでCADを扱う技術力を証明できます。
機械設計エンジニアは製品の設計や図面作成、試作モデルの作成、シミュレーションなどの業務において、CADを用いて設計データの作成や修正、解析を行います。機械設計においてはCADを用いることが多く、設計の効率化や精度向上、データ共有の円滑化につながるのでCADの技術力というのは重要になります。
本試験は、2次元CAD利用技術者検定と3次元CAD利用技術者検定の2種類に分かれており、それぞれ以下のような階級があります。
| 検定名 | 級 |
|---|---|
| 2次元CAD利用技術者検定 | 基礎 |
| 2級 | |
| 1級(建築) | |
| 1級(機械)、1級(トレース) | |
| 3次元CAD利用技術者検定 | 2級 |
| 準1級 | |
| 1級 |
機械設計エンジニアとしては、2次元と3次元のどちらを取得しても業務に活用できますが、目的に応じた選択が重要です。
4.CAD実務キャリア認定制度CAD実務マスター認定試験
CAD実務マスター認定試験は、CADを活用した実務能力を評価する試験です。CAD技術者やCAD教育を受けた人を対象とし、実務的なスキルや知識の習得度を測定します。筆記試験と実技試験の二部構成となっています。
筆記試験ではCAD導入時の確認事項、著作権を含む関連法規、建築用語などが出題され、知識の正確性が問われます。実技試験では、複数枚の参考図をもとに指示書に従って図面を作成する能力が評価されます。
CADを活用した正確な図面作成や指示書に基づく設計スキルを証明できるため、機械設計エンジニアにとって有効です。「CAD実務トレーサー認定試験」や「CADアドミニストレータ認定試験」とともに、CAD実務キャリア認定制度の一環として運営されています。
5.トレース技能検定
トレース技能検定は、機械や建築、地図などの図面を清書する「トレース」の技術を評価する検定です。トレースの正確性や技術的な理解を証明する資格であり、業務で必要なスキルを測る指標となります。機械設計において、トレースは設計者のスケッチやラフ図を正確な図面に仕上げ、製造や組立の工程で設計意図を的確に伝えるために必要な技術です。
この検定は、4級・3級・2級・1級に分かれており、それぞれ実技試験と理論試験を受験する必要があります。4級では線の基本や初歩的な知識が問われますが、1級では複雑な図面のトレース技術、日本工業規格における応用知識、専門分野に関する内容が求められます。特に2級以上では、基礎知識に加えて、精密な寸法管理や複雑な図面の正確な作成などのより幅広い応用力が必要とされます。合格することで高度なトレース技術と設計図の理解力を持つことを証明できます。
6.技術士(機械部門)
技術士(機械部門)は、科学技術分野における高度な専門知識と実務経験を有する技術者に与えられる国家資格です。技術士資格を取得することで、機械設計における理論的知識や解析・評価能力などの知識・スキルを保有していることを証明できます。
試験では機械工学の専門知識や設計・解析能力に加え、問題解決力や倫理観を問う筆記試験が実施され、口頭試験では技術者としての実務経験や応用力が評価されます。
技術士の資格を取得するには、まず一次試験に合格し「修習技術者」となる必要があります。その後、「技術士補」として登録して指導技術士のもとで一定年数の実務経験を積むことで二次試験の受験資格を得られます。
技術士は製品開発や設計の最適化、品質管理、トラブルシューティングなどの業務に活用できます。専門技術者としての信頼性を高めることができるため、より高度な技術開発やコンサルティング業務に従事できる可能性なども広がります。
7.計算力学技術者資格認定
計算力学技術者資格認定は、一般社団法人 日本機械学会が運営する資格であり、計算力学に関する技術レベルを客観的に評価することを目的としています。
計算力学とは、コンピュータを用いて力学挙動を解析・評価する技術であり、デジタルエンジニアリングの分野で重要な役割を担っています。機械設計では製品の強度や耐久性、熱影響などを事前にシミュレーションし、安全性や性能を確認するので計算力学が必要になります。
この資格は、機械設計やCAEを活用するエンジニアにとって、専門知識を証明する有効な手段となります。CAEソフトウェアを使用するだけでなく、その解析結果の物理的な意味を正しく理解し、活用できるスキルを持つことも証明できます。
試験は初級・2級・1級・上級アナリストの4つのレベルに分かれており、初級は制限なしで受験可能ですが、2級以上は書類審査が必要です。
8.電気主任技術者
電気主任技術者は、電気事業法で定められた国家資格であり、電気設備の安全管理を担う能力を証明するものです。この資格を取得することで、電気の構造や管理に関する深い知識を習得でき、電気設計分野との連携も円滑になります。
特に、モータや電動機を使用する機械設計では、電気的な負荷やエネルギー効率を考慮する必要があります。電気主任技術者の知識があれば、電動機の選定や電気系統の安全設計を行い、より信頼性の高い機械設計が可能になるでしょう。
電気主任技術者は、エンジニアとしての専門性を広げ、より高度な設計や管理業務を行うのに有用な資格です。
9.危険物取扱者
危険物取扱者は、消防法に基づく国家資格であり、危険物の貯蔵・取扱いに関する専門的な知識と技術を証明するものです。資格は甲種・乙種・丙種の3つの区分に分かれ、取り扱える危険物の範囲が異なります。
| 甲種 | すべての種類の危険物 |
|---|---|
| 乙種 | 第1類(酸化性固体) |
| 第2類(可燃性固体) | |
| 第3類(自然発火性物質および禁水性物質) | |
| 第4類(引火性液体) | |
| 第5類(自己反応性物質) | |
| 第6類(酸化性液体) | |
| 丙種 | 引火性液体 |
機械の潤滑油やグリースなど、一部の工業製品には危険物に該当する成分が含まれることがあります。資格を取得することで、機械設計における安全性の確保や適切な材料選定に貢献できるでしょう。
機械設計エンジニアの資格取得における注意点
機械設計エンジニアの資格を取得する時には、押さえておいたほうがよい注意点がいくつかあります。
受験資格があるものがある
機械設計エンジニアに関係する資格のなかには、受験資格があるものがあることに注意してください。資格の中には、誰でも受験できるものから一定の経験や卒業資格などの条件を満たす人しか受験できないものがあります。例えば、以下のような条件があります。
| 資格名 | 条件 | 必要な実務経験 |
|---|---|---|
| 機械設計技術者試験2級 | 工学系の大学院・大学・高専専攻科を卒業 | 3年 |
| 工学系短大・高専・専門学校を卒業 | 5年 | |
| どちらにも該当しない場合 | 7年 | |
| 機械設計技術者試験1級 | 工学系の大学院・大学・高専専攻科を卒業 | 5年 |
| 工学系短大・高専・専門学校を卒業 | 7年 | |
| どちらにも該当しない場合 | 10年 | |
| 技能士(機械・プラント製図技能士) | 1級 | 7年以上 |
| 2級 | 2年以上 |
資格の中でも上級になると受験資格として実務経験が必要になってくるケースが多いので、事前に確認しておきましょう。
資格も大事だが実務も
機械設計エンジニアの資格取得における注意点として、資格は大事ですが実務も重要であるということを理解しておかなければなりません。
機械設計エンジニアでは知識が重要とされますが、実務能力も重要視されます。資格を取得することで専門知識や基本的なスキルを持っていることを証明できますが、実際に現場で起こる課題への対応、実務の場面での対応、チームでの業務の遂行ができるかはわかりません。
そのため、企業は資格を取得しているというだけでは採用をしてくれない可能性があります。実務能力がどれくらいあるのかも確認されるので、設計や開発プロジェクトの経験があるか、どのような実務能力があるのかをアピールする必要があります。これまでにどんな仕事をしてきたのか、どのようなものを作ってきたのかを具体的に説明し、実績として示すのがよいでしょう。
働いたことがなくとも大学で取り組んだ設計課題や研究テーマやマネジメント経験などをアピールするのもよいかもしれません。資格と実務経験の両方をバランスよく身につけることで、転職市場において強みを発揮できるでしょう。
目的にあった資格を選ぶ
機械設計エンジニアが資格を取得する際は、目的に合った資格を選ぶことが重要です。業務や将来のキャリアと関係のない資格を取得しても仕事で活かせないですし評価につながらないので、あまり意味がありません。自身の業務に活かせ、将来のキャリアにつながる資格を取得しましょう。
適切な資格を選ぶためには、まずキャリアプランを設計することが重要です。将来どのようなポジションを目指すのか、機械設計・製造においてどのようなことができるようになるのかなど、将来目指すキャリアのプランを作ることで、必要な資格が明確になります。
例えば、管理職を目指すのであればマネジメント関連の資格が必要でしょうし、独立を目指すならコンサル関連の資格なども有効でしょう。資格取得を検討する際は自身の将来像を描き、それに基づいた資格を選ぶことから始めましょう。
学習計画を明確にする
機械設計エンジニア関連の資格取得を目指す際は学習計画を明確にしましょう。
機械設計に関する資格の試験範囲は広いことが多いので、計画を立てずに勉強を進めるとどこから手をつければよいのか分からなくなり、効率が悪くなってしまいます。計画を立てることで進捗を管理しやすくなり、効率的に学習を進められるでしょう。
また、資格のなかには実務経験が求められることもあるので、数年単位で計画を立てることも必要になってきます。どんな職種を何年経験するか、どのような順序でどんな資格を得ていくかなども考えてキャリアを選んでいかなくてはなりません。
機械設計エンジニアへの就職・転職ならベスキャリ機電で
機械設計エンジニアは資格を取得することで専門知識の証明や信頼性向上というメリットが得られます。ただし、転職においては資格の取得だけでは採用してもらうことは難しい場合があります。実務能力を身につけるとともに、自身の能力や強みをアピールしなくてはなりません。
機械設計エンジニアへの転職を成功させるためには資格取得も有効ですが、転職エージェントの活用も有効です。エージェントは多くの転職者を見てきているので、キャリアや強み、何をアピールすべきかについてアドバイスしてくれます。
「ベスキャリ機電」は、機電エンジニアに特化した転職エージェントです。15年以上の運営実績があるので全国の企業とのネットワークがあり、非公開求人も多数掲載しています。
業界知識の豊富な専任のアドバイザーがひとり一人につき、キャリアの方向性や自身の強み、企業が求めるポイントといったアピールすべき内容を的確にアドバイスしてくれます。
求人紹介だけでなく、履歴書・職務経歴書の添削、面接対策、就業後のアフターフォローまで対応しており、特に初めての転職で不安を抱えている方にとって心強い存在です。最適なキャリアを実現するために、「ベスキャリ機電」をぜひ活用してください。